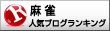意外と重要!牌効率を語るに欠かせないカンチャンの優劣を解説

麻雀の牌効率を勉強するとペンチャンよりカンチャン、カンチャンより両面が強いことが分かってきます。
両面の中では更に![]()
![]() や
や![]()
![]() など
など![]() –
–![]() ,
,![]() –
–![]() 待ちは端が出やすいので最も強く、逆に真ん中寄りの
待ちは端が出やすいので最も強く、逆に真ん中寄りの![]()
![]() や
や![]()
![]() は待ちも真ん中寄りの
は待ちも真ん中寄りの![]() –
–![]() ,
,![]() –
–![]() となり他家から出にくいので両面の中では弱いとされています。
となり他家から出にくいので両面の中では弱いとされています。
意外と知られていませんがカンチャンの中にも優劣があります。カンチャンの種類は![]()
![]() ,
,![]()
![]() ,
,![]()
![]() ,
,![]()
![]() 、
、![]()
![]() ,
,![]()
![]() ,
,![]()
![]() の計7種。この中で
の計7種。この中で![]()
![]() ,
,![]()
![]() ,
,![]()
![]() の3種が強く、残りの4種は弱いと言われます。なぜだか分かりますでしょうか。
の3種が強く、残りの4種は弱いと言われます。なぜだか分かりますでしょうか。
前者は両面変化が2種に対し、後者は1種だからです。
※以下、![]()
![]() ,
,![]()
![]() ,
,![]()
![]() のカンチャンを【強カンチャン】、
のカンチャンを【強カンチャン】、![]()
![]() ,
,![]()
![]() ,
,![]()
![]() ,
,![]()
![]() のカンチャンを【弱カンチャン】とします。
のカンチャンを【弱カンチャン】とします。
牌効率の基本はブロックごとに『面子になる有効牌が何種何枚か、両面に変化する有効牌が何種何枚か』を考え、それが少ないブロックを切ることです。
ペンチャンとカンチャンを比較するとカンチャンの方が強いのも同じ理由です。両方とも面子になる有効牌は1種4枚で同じですが、両面になる有効牌はペンチャンが0に対してカンチャンが1種4枚もしくは2種8枚になるからです。
それでは以上の内容を踏まえて実戦で何を切るか考えてみたいと思います。

こちらは3着で迎えたオーラス5巡目、上がればラス回避、満貫ツモで2着浮上の場面です。
カンチャンターツが多くあり7ブロックとなっています。どれか切るのが正解か考えてみてください。
・・・
・・・
・・・
候補となるのは![]()
![]() 、
、![]()
![]() 、
、![]()
![]() 、
、![]()
![]() のどれかだと思います。
のどれかだと思います。
正解は![]() (
(![]() )切りになります。
)切りになります。
まず候補となるカンチャンターツ4種はいずれも両面変化1種の弱カンチャンなので、単体で見た場合の優劣はありません。そこで次に見るのが他の牌との重なりです。
それぞれ両面に変化する有効牌をツモった後の、隣り合う牌も合わせた形を記載すると以下の通りです。
![]() ツモ▶︎
ツモ▶︎![]()
![]() の両面ターツと
の両面ターツと![]()
![]() のカンチャンターツ
のカンチャンターツ
![]() ツモ▶︎
ツモ▶︎![]()
![]() のカンチャンターツと
のカンチャンターツと![]()
![]() の両面ターツ
の両面ターツ
![]() ツモ▶︎
ツモ▶︎![]()
![]() のカンチャンターツと
のカンチャンターツと![]()
![]()
![]() の1面子
の1面子
![]() ツモ▶︎
ツモ▶︎![]()
![]()
![]() の1面子と
の1面子と![]()
![]() のカンチャンターツ
のカンチャンターツ
上2つは両面に変化する有効牌をツモるとカンチャンターツが両面ターツに変化していますが、下2つはカンチャンターツのままです。
それは下2つの場合、両面に変化する有効牌が隣り合う両面ターツと被って吸収されてしまうからです。
上がるために必要な4面子1雀頭の5ブロックに余りがない場合は、下2つの場合でも他に面子ができて手が進むので問題ありません。ですが今回の場合は7ブロックと余っているので不要なブロックを切る必要があります。
両面変化の有効牌をツモってもカンチャンのままならそのブロックは不要です。![]()
![]() と
と![]()
![]() の両面変化の有効牌が実質0のカンチャンターツということになります。
の両面変化の有効牌が実質0のカンチャンターツということになります。
切る候補が2つに絞られました。![]()
![]() と
と![]()
![]() の優劣は共に4枚残りなので打点で考えます。
の優劣は共に4枚残りなので打点で考えます。![]() をツモるとタンヤオが消えますが
をツモるとタンヤオが消えますが![]() をツモるとタンヤオになる可能性が残ります。なので
をツモるとタンヤオになる可能性が残ります。なので![]()
![]() のカンチャンターツを払います。
のカンチャンターツを払います。
以上となりますが重要なのはカンチャンの中にも優劣があること、他のブロックと有効牌が被る部分は不要であること、打点との兼ね合いも必要であること、の3点です。
序盤にカンチャンターツの優劣を見極めて打牌選択をするのは地味ですが、こういった細かい地味な所で麻雀の上手い下手の差がつきます。
さて、弱カンチャンの優劣を見てきましたが強カンチャンにも触れておきたいと思います。
![]()
![]() ,
,![]()
![]() ,
,![]()
![]() は全て両面変化2種のカンチャンターツですがタンヤオが濃厚な場面では
は全て両面変化2種のカンチャンターツですがタンヤオが濃厚な場面では![]()
![]() が最も優位になります。
が最も優位になります。
例えば以下のような状況について考えてみます。
東1局西家4巡目、ドラは![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
ドラの![]() が暗刻なのでタンヤオドラ3を狙います。萬子で3面子、
が暗刻なのでタンヤオドラ3を狙います。萬子で3面子、![]() をヘッド固定として、残り1面子を
をヘッド固定として、残り1面子を![]()
![]() と
と![]()
![]() のどちらかで作ることになります。
のどちらかで作ることになります。
![]()
![]() はタンヤオになる両面変化が
はタンヤオになる両面変化が![]() のみ、
のみ、![]()
![]() は
は![]() と
と![]() の2種あるので
の2種あるので![]() を切ります。
を切ります。
両面変化の有効牌は強カンチャンの3つはどれも2種8枚で同じですが、![]()
![]() はタンヤオを狙う場面では最も強いカンチャンターツとなります。
はタンヤオを狙う場面では最も強いカンチャンターツとなります。
では、カンチャンターツの中で![]()
![]() が1番強いかというと実はそうではありません。
が1番強いかというと実はそうではありません。
例えば以下のような状況について考えてみます。
東1局西家4巡目、ドラは北
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
![]()
![]() も
も![]()
![]() も共に両面変化2種8枚となりますが、リャンカンチャンになった場合の両面変化の有効牌には差が出ます。
も共に両面変化2種8枚となりますが、リャンカンチャンになった場合の両面変化の有効牌には差が出ます。
![]() ツモ▶︎
ツモ▶︎![]()
![]()
![]() となり両面変化の有効牌は
となり両面変化の有効牌は![]() の1種4枚
の1種4枚
![]() ツモ▶︎
ツモ▶︎![]()
![]()
![]() となり両面変化の有効牌は
となり両面変化の有効牌は![]()
![]() の2種8枚
の2種8枚
一般的に全5種類のリャンカンチャンのうち、![]()
![]()
![]() のリャンカンは両面変化2種になり最も強い形になります。
のリャンカンは両面変化2種になり最も強い形になります。
一方で、今回の![]()
![]()
![]() を含め
を含め![]()
![]()
![]() ,
,![]()
![]()
![]() ,
,![]()
![]()
![]() など他のリャンカンチャンは両面変化1種となります。
など他のリャンカンチャンは両面変化1種となります。
なので、単純な手広さで言うと![]()
![]() ,
,![]()
![]() のカンチャンが強く、タンヤオ狙いなら
のカンチャンが強く、タンヤオ狙いなら![]()
![]() が強いということになります。
が強いということになります。
カンチャンの優劣についてまとめると次のようになります。
| カンチャンの種類 | 両面変化の有効牌 | 特徴 | |
| 弱カンチャン | |||
| 弱カンチャン | |||
| 強カンチャン リャンカンチャンでも両面変化2種8枚で手広い | |||
| 強カンチャン タンヤオ狙いでは最も強い | |||
| 強カンチャン リャンカンチャンでも両面変化2種8枚で手広い | |||
| 弱カンチャン | |||
| 弱カンチャン |
カンチャンの優劣を意識すべき場面は多くはありませんが、意識して打牌選択ができるようになると確実にテンパイスピードは早くなりますし打点アップも期待できます。
是非カンチャンの優劣の理解を深めて実戦で活かせるようにしていただければと思います👍